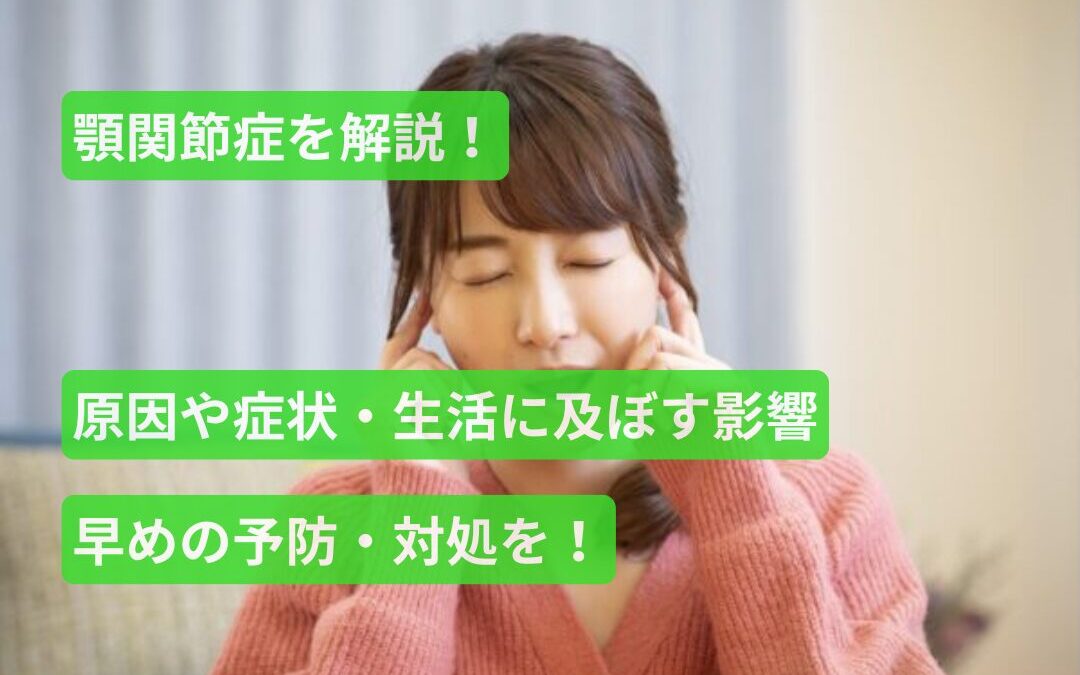実は7~8割の人は顎に大なり小なり不調を訴えることが分かっています。
顎の関節に痛みや障害が現れると、生活そのものに多大な影響を与えてしまいます。
このブログでは、顎関節の構成や症状・特徴・対処方法などをお話していきます。

顎関節の構成は、下顎骨の下顎頭と側頭骨の下顎窩により構成されます。
また顎関節の間に存在する関節円板という衝撃吸収剤の役割をする組織と
関節の動きをスムーズにする潤滑油、滑液などによって顎関節は正常な状態を保ちます。
顎関節症では、関節を構成する骨や関節を支持する組織に何らかの異常が生じて
■顎の運動で痛みが出る
■開口や閉口に違和感や制限がある
■顎の動作時にクリック音がする
■咀嚼時に物が噛みにくい
上記の症状や、他の不調を引き起こします。
また、顎関節周囲の骨や筋肉が症状を悪化させるケースも多いです。
発症している人に男女差はあまりないといわれていますが
統計や私の経験上、女性に多く症状が出現しているように思えます。
また、20~40歳代に好発しているのが特徴です。
冒頭でも触れましたが、人口に対して7~8割の人が大なり小なり
顎関節に何らかの違和感や障害を抱えていると言われています。
ですが、症状が深刻化しない限り見過ごしたり放置したりされる傾向です。
顎関節症が悪化し、より症状が出てから辛い思いをしたときには
改善したり、予後が良くなるまでかなりの時間がかかることもあります
今の段階で、顎関節に何らかの自覚症状がなくても顎関節症の予備軍である可能性もあります。
以下の項目に対して、いくつか該当する人は顎関節症の可能性が示唆されますので
日常生活で顎関節に違和感がある方は、行ってみてください。
■第2~4指の3本を縦に揃えて、口に入れることができない。
■食べ物の咀嚼や、長い間の会話で顎がだるくなったり疲れやすい。
■大きなあくびができない。
■口の開閉動作で耳の辺りに音がする。
■かみ合わせが変わった感覚がある。
■頭痛や肩こりが頻繁、悪化している。
また、自身の生活習慣からも発症に関わるものもあります。
■歯ぎしりをしている、と自覚また言われたことがある。
■朝~夜を通して、歯をくいしばっている。
■食事中に左右で、どちらか一方で噛む癖がある。
■神経質で、ストレスに対して体調が左右されやすい。
■睡眠の質が悪い、途中覚醒がある。
など、心身の状態が安定していない場合でも顎関節症を誘発する原因になります。
当てはまる項目が多いほど、顎関節症である確率は高くなっていきます。
顎関節症は組織の障害レベルによって病態は異なります。
病態によっては、保存療法が適応できないケースもあり手術適応の可能性もあります。
なので、顎関節に障害を与えないようにかすかな症状があれば予防意識や
初期の段階で、先程の項目があれば治療を行えう専門機関で予防治療を行いましょう。
顎関節は以下の分類があります。
・1型:咀嚼筋障害
・2型:顎関節障害(関節包・靱帯の痛み,軟部組織の慢性病変)
・3型:関節円板障害(関節円板の異常病変,クリック音を認める)
・4型:変形性関節症(顎関節を構成する骨に変形が生じる)
主に、こういったステージに病態・病変は分けられます。
1型:咀嚼筋の障害

顎関節症は、実はいくつか種類があります_20241217_2
顎関節の主動筋である、この4つの筋肉に制限や硬結などが原因で痛みがでます。
2型:関節包・靱帯の障害

2型の障害は下顎骨と他頭蓋骨の連結を補強する下顎の外側靱帯、その他各靱帯や
関節包とよばれる滑液が満たされ、関節の摩擦を軽減し運動を円滑にする組織に
機能制限などの障害が起きたものが2型に該当します。
3型:関節円板の障害

顎関節を構成する下顎頭と下顎窩の間には関節円板という軟部組織があります。
本来は、この関節円板と下顎頭が正常に動くことで開閉や咀嚼運動は
制限がなく行われるますが、この関節円板が偏位したり嵌頓状態に陥ることで
痛みや、クリック音(関節の雑音)が出現した状態を3型に分類されます。
3型は、自覚症状にもよりますが保存療法よりも手術を行います。
4型:変形疾患
関節円板の破壊や、関節包や下顎頭などの構成箇所の変形による障害です。
このステージへの発展起因は、2・3型状態の放置・悪化による段階的な進行
また正しい位置での関節運動が不可能になり、骨や軟部組織に衝撃や衝突を繰り返し
重症化した状態です。
この状態では、保存療法はほぼ適応不可ですので手術を行います。
当院は1・2型の状態は大きく効果が期待できますが
3・4型に関しては、対処・緩和程度です。病院との併用をオススメします。
■顎関節の痛み
一般的な病態は筋・筋膜性の疼痛です。
頭頚部および口腔顔面領域の持続性疼痛が最も一般的な原因でもあります。
筋・筋膜疼痛の特徴では局所的な鈍い、疼くような痛みです。
筋肉の収縮や伸張などの機能にて痛みは増強します。
活動的な状態の筋肉の硬結を圧迫すると、ジャンピングサインと呼ばれる
逃避反応が現れる程の鋭い痛みを局所に生じたり、離れた部位の
歯や眼・側頭部や頸部などの関連痛を起こします。
また滑膜炎、関節包あるいは円板後部結合組織における炎症性の状態により
下顎頭と接するこれら組織に炎症が生じ神経が侵害されて
顎関節の運動時に下顎頭の動きが起因し刺激されて痛みが生じることもあります。
■開口障害
先程の述べたように、本来正常な状態であれば第2~4指を揃え
口を大きく広げれば、その幅は通過します。その幅は、約40mmほどです。
徐々に、開口動作が違和感や制限が現れた場合は咀嚼筋の病態を疑います。
突然開かなくなった場合には、関節円板の偏位や嵌頓を疑うことが多いです。
他の原因には、軟部組織の性質変化や組織癒着なども障害を惹起します。
■関節雑音

咀嚼や開口時にガクンっ・ゴリゴリといった関節音が現れます。
最も多い原因は、関節円板の偏位などによる開口時における反復した関節円板の移動制限です。
前方に転位した関節円板が、開閉口に伴って下顎頭が前後に動く際に下顎頭上に戻ったり
再度転位し嵌まった時にクリック音(雑音)が発生します。
その他の雑音として、下顎頭や関節窩、関節円板が変形性障害を起こして
下顎頭と直接または間接的に擦れ合うことによっても音は発生します。
また、関節雑音と痛みは単に関連性は少なく、音が大きいからといって
痛みが強烈に現れるない場合もあります。
こういった症状が、ひとつ以上あれば迅速に対処が必須です。
日常生活のなかで、顎への痛みや制限を感じた場合
まず歯科医院(口腔外科)で検査や治療を受けるのが一般的です。
そこで、X線(レントゲン)や他の画像診断法で顎関節・口周囲を撮影し
あきらかな顎関節や関節円板などの変性があった場合(3・4型)は
外科的な処置で対応する確率が高いため、歯科医師の判断で治療方針が決まります。

また、スプリント療法とよばれる患者専用のマウスピースを作製して
就寝時に装着する対応などで経過を観察することもあります。

診断内容が1・2型だった場合、鍼治療や手技療法などで顎関節や
咀嚼筋の障害を軽減・消失させ、痛みや口の開閉動作を正常に近づけます。
鍼治療は、深部への介入により筋肉や靱帯などの組織にアプローチが可能です。
また鎮痛・鎮静効果や炎症除去効果も鍼治療で獲得できるため
早期的な症状変化が見込める可能性があります。
ただ、障害が現れている箇所だけで症状が変化しないこともあります。
例えば、ストレートネックによって頭部の前方偏位によって
顎関節に負担を与え症状を増悪させていたり
胸郭の拡張や収縮に制限があることで、呼吸が適切に行われず
大胸筋をはじめとした胸郭周囲の呼吸筋の活動機能が低下し
肩や頸部の筋肉で代償することで顎関節に少なからず影響がでると考えられます。
頭部の重さは、自身の体重の1/10ぐらあるのでそれを支え続ける
組織器官の状態を整えることは、顎関節症の改善につながります。
もちろん、この考えで全ての顎関節症が改善しないこともあります。
他の身体からの原因や、自身の精神状態なども関係します。
※3・4型の顎関節症も痛みや関節障害の対処療法は可能です。
他にも、一人ひとりの顎関節や身体の状態に合わせて最善の治療を提供いたしますので
お悩みの方は、まずは当院で状態を診させていただければと思います。
予約はこちら → 光幸はりきゅう院接骨院|ホットペッパービューティー
鍼施術は、初回¥3500~です。
光幸はりきゅう院・接骨院 代表:庄司有希