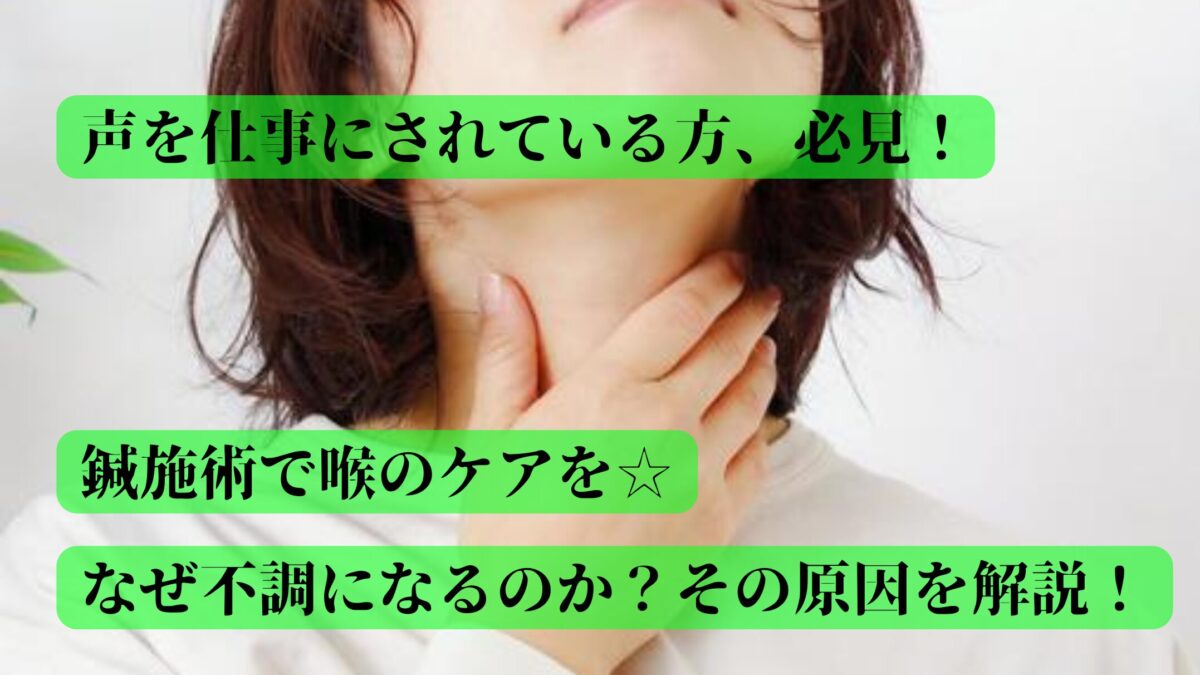鍼施術によって「声が出やすくなる」理由は、身体的・神経的メカニズムに基づいています。
発声には呼吸、声帯、共鳴腔(喉、口、鼻など)といった複雑な連携が関わっており
鍼灸はそれらに働きかけることが可能なのです。
◇鍼施術が発声に与える良い影響
1. 筋緊張の緩和
発声に関わる筋肉(喉周辺、首、肩、胸、横隔膜など)が過緊張していると、声が出しづらくなります。
鍼はこれらの筋肉の緊張を和らげ、滑走性や柔軟性に効果が期待できます。
例として、胸鎖乳突筋や斜角筋、喉頭周辺の筋肉が緩むと声帯の動きが
スムーズになることが分かっています。
2. 自律神経の調整
鍼灸は副交感神経を優位にし、リラックス状態を促します。
緊張やストレスによって交感神経が優位になると、喉が締まり
声がかすれる・出しづらくなることがあります。
鍼は副交感神経を優位にするので、喉が開きやすくなり自然な発声が可能になります。
3. 局所の血流改善
喉周辺や声帯に関わる組織の血流が良くなると、声帯の動きが滑らかになります。
血流が促進されることで炎症の軽減や疲労回復も早まります。
☆どこを施術するのか?
ツボ(経穴)への刺激で、身体の気の巡りを良くし不調を緩和させます。
全身調整(手や腹部・頭部など)+局所(首の前側や鎖骨)の経穴を用いて
発声だけではなく喉の不快感や、呼吸のしづらさを解消させます。
◎どんな人にオススメ?
○声を仕事に使う人(歌手、教師、アナウンサーなど)
○緊張やストレスで喉が締まりやすい・苦しい人
○声がかすれる、出しにくい、出し続けると疲れるといった症状がある人
☆発声に関係する筋肉を紹介!声の仕事の方、要チェック
声帯を構成する筋肉は、発声の「要」です。
これらの筋肉は喉頭に位置し、音の高さ・大きさ・質を調節するために
繊細に働いています。
◇声帯に関わる主要な筋肉
○甲状披裂筋(こうじょうひれつきん)
声帯そのものを構成する筋肉で、声帯を短く・太くすることで、低い声を出すのに働く。
その一部は、発声の微調整を担当をし、声の張り・音色のコントロールに重要。
○輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん)
声帯を引っ張って伸ばす作用があり、高い声を出すときに使う。
声帯がピンと張られることで振動数が上がり、高音になる。
○後輪状披裂筋(こうりんじょうひれつきん)
唯一の声帯を開く筋肉で、呼吸時に声帯を開くことで、空気が通るようにする。
これが働かないと声帯が閉じっぱなしになり、息ができなくなる。。
○側輪状披裂筋(そくりんじょうひれつきん)
声帯を閉じるために使う筋肉。
発声時には声帯を閉じて、空気の通過で振動を起こす。
○披裂間筋(ひれつかんきん)
披裂軟骨同士を引き寄せて、声帯の完全閉鎖を助ける。
声に力を入れたいとき、強く発声したいときに重要!
◇発声における筋肉の協調動作
・高音を出すとき:輪状甲状筋が優位に働き、声帯を張る。
・低音を出すとき:甲状披裂筋が働き、声帯を短縮・弛緩させる。
・息を吸うとき:後輪状披裂筋が声帯を開く。
声を出すとき:側輪状披裂筋と披裂間筋が声帯を閉じる。
◇喉を支配する神経
声帯の筋肉は主に迷走神経(第10脳神経)により支配されます。
その枝の☆反回神経☆上喉頭神経
この神経が障害されると声帯の動きに異常が出て、声枯れや発声障害が起こります。
◇どう声帯の筋肉にアプローチするのか?
鍼を用いて、声帯の筋肉や頸部や頭部の筋肉を中心に
筋緊張を緩和させ、無理なく声が出るような施術を行います。
身体の緊張=交感神経優位の状態なので、全身調整で
副交感神経の働きを優位にすることで、さらに効果を期待できるようになります!
☆声が出づらくなる理由/ストレスとの関係性
声とストレスには深い関係があります。
ストレスが原因で声が出づらくなる理由はいくつかあり
身体的・心理的な要素が複雑に絡み合っています。
◇なぜストレスで声が出づらくなるのか?
○筋肉の緊張
ストレスを感じると、身体のさまざまな筋肉が緊張します。
喉や声帯まわりの筋肉もその対象で、緊張によって声帯がうまく開閉できず
声がかすれたり、出にくくなったりします。
○呼吸が浅くなる
ストレスを感じると、無意識のうちに呼吸が浅く早くなります。
声を出すには腹式呼吸(深い呼吸)が必要ですが、浅い胸式呼吸では
十分な声量や響きが出せず、声が弱々しくなったり詰まったりします。
○自律神経の乱れ
ストレスは交感神経を過剰に刺激し、自律神経のバランスを崩します。
これにより唾液の分泌が減少して喉が乾燥したり、声帯の動きが悪くなったりします。
○心因性の発声障害(心因性失声)
強いストレスや精神的ショックが原因で、医学的には声帯に異常がないのに
声が出なくなるケースもあります。
これは「心因性失声症」や「機能性発声障害」と呼ばれ、心理的なケアが必要になります。
◇対策方法
深呼吸を可能な限り、意識をして緊張をほぐす。
鍼を施術で、ストレスを緩和や声帯に関連する筋肉の緊張にアプローチ。
などで、少しずつ身体の状態を変えていく必要があります。
声を仕事にされている方は、身体の疲労やストレスを感じやすい方が多い印象です。
身体は異変が現れてからでは対処は遅くなってしまいます。
自分自身の身体からの、声に無視をせずケアをしていきましょう。
お困りの方は、ご相談ください。
光幸はりきゅう院・接骨院 代表:庄司有希